|
第16回認定試験(2024年10月26日予定)対策講座
|
|
| 一般財団法人 国際技能・技術振興財団 認定資格 |
 |
|
 |
|
 |
|
●食生活と認知症予防
食生活を改善することは、認知症予防だけでなく、健康を維持するためにも大切なことです。
認知症は高齢者になってから発症する例が多いのですが、それは若いころからの食生活が大きく
関わっていることを認識しておく必要があります。
脳血管性の認知症は、その発症原因に脳梗塞・脳出血などの血管の病気が深く関わっています。
高血圧、動脈硬化などに基づく生活習慣病です。これらの血管の病気は、適切な食生活で進行を食い止め
改善することができます。特に動脈硬化を防ぐための食生活の改善に心がけることが、認知症の予防に
つながります。
●認知症予防と食習慣
食生活を改善することが健康への第一歩です。
食事に大きく関係する生活習慣病といわれる糖尿病、高血圧症を患っている人は、脳血管の
動脈硬化が進み、結果として認知症の発症率が高くなります。アルツハイマー型認知症も生活習慣に
大きく関係し、特に糖尿病にかかっている人の発症率は2.1倍といわれ、血糖値を抑えれば認知症の
予防にもつながる可能性があります。
栄養バランスのよい食事を心がけ、生活習慣を改善していくことが、認知症予防の近道といわれて
います。
|
|
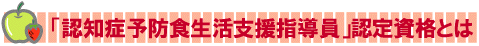 |
| □ |
■認定資格の目的
急増する認知症の新たな対応施策として、従来の「早期発見、早期治療」から、現在は「症状の初期
段階からの予防支援」「発症する前の予防」を中心とした予防対策に重点がおかれています。
認知症の予防対策としては、適度な運動やバランスのとれた食事が、認知症予防だけでなく
健康を維持するうえで重要といわれています。
しかしながら、認知症予防の専門知識や技術をもった人材が不足しており、予防対策を実施して
いくには、地域社会活動において支援者や指導者、相談者の育成が急務となっています。
本認定資格は、専門職の人材を育成し、それらの専門職の地位の向上と資質の向上を目的に、
その知識やスキルを評価し認定する資格です。
■食生活支援指導員の役割
今後は、高齢施設や地域社会において認知症予防の知識を高めていく必要があります。食生活
支援指導員は、認知症予防を目的とした「食生活改善」に対して多くの人に理解を広め、高齢者の健康維持と
認知症予防支援活動を通して地域社会活動の支援者や相談者として活躍が期待されています。
■食生活支援指導員の活躍の場
①地域社会活動において認知症予防 「食生活改善」の提案、指導及び相談
②介護施設、高齢者施設における 「食生活改善」の提案、指導及び相談
③地域における認知症予防を目的とした食生活支援活動指導者、相談者の育成
④認知症予防を目的とした講習会、セミナー等の開催及び講師活動
⑤地域における認知症予防を目的とした食生活支援センター等の開設
⑥認知症予防を目的とした広報誌の発行及び情報の提供
⑦認知症を予防するライフスタイルの提案及び指導 |
|
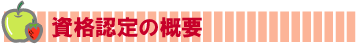 |
|
| □認定団体/ |
一般財団法人国際技能・技術振興財団
|
|
|
| □認定試験/ |
年2回(原則3月、10月) |
|
|
| □受 験 料/ |
7,000円 |
| |
|
| □受験資格/ |
受験資格には資格、年齢、経験は問われません。 |
|
|
| □認 定/ |
認定試験の合格基準(60%)を満たした方には「認定証」を交付します。
ただし、認定料3,000円を納付のこと。 |
| |
|
|
|
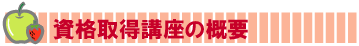 |
|
| □教 場/ |
■横浜教室/読売文化センター横浜(横浜そごう9F) |
|
■大阪教室/毎日文化センター大阪(毎日新聞ビル2F) |
| |
|
|
|
|
| □開講予定/ |
年2回(原則1月・7月) |
|
|
|
|
| □開講講座/ |
全4コース |
|
|
|
|
| □受講定員/ |
15名 |
|
|
|
|
| □受講対象/ |
◎受講資格に制限はありません。
・認定試験の受験を希望される方
・食生活指導に関心のある方
・認知症予防、介護予防に関心のある方
・介護・医療施設スタッフで指導員を希望される方
・介護・看護職の方でスキルアップを希望される方
・地域の社会活動やボランティア活動で活躍の方
・高齢者の食生活に関心のある方
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
全国有名書店にて発売中! |
| □受講料/ |
・横浜:46,200円(税込、テキスト・資料費別3,300円) |
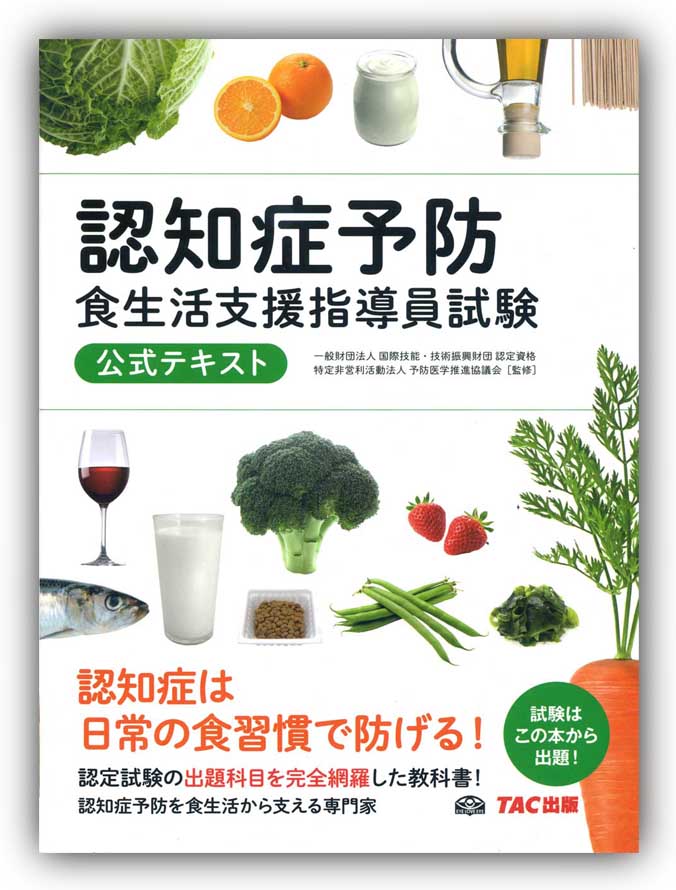 |
| |
・大阪:43,560円(税込,、テキスト代別2,300円) |
|
・※入会金別 |
□使用教材/
|
「認知症予防食生活支援指導員
試験公式テキスト」
(TAC出版)を使用 |
|
|
□予定講師/
|
【横浜代表講師】合原 康行
・三浦市立病院、日本鋼管病院などで栄養管理責
任業務などを担当。
・元神奈川県栄養士会副会長、神奈川県病院
栄養士協議会副会長
・横浜市医師会保土ヶ谷看護学校講師等を経て、
現在、東京マスダ学院調理師専門学校講師
【大阪教室・代表講師】横井智恵子
・フードコーディネーター、テーブル
コーディネーター講師資格
・食生活アドバイザー公認講師
・京都光華女子短大講師
|
認知症予防食生活支援指導員試験
公式テキスト
(A5版220ページ)
書店:2,420円(税込み)
|
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
|
 |
■講座は途中入会可能。次回は2025年1月講座募集予定 |
|
|
カリキュラム内容 |
| 横浜会場 |
大阪会場 |
|
読売文化センター
横浜・提携講座 |
毎日文化センター
大阪・提携講座 |
|
| 2024年7月講座 |
2024年7月講座 |
|
| 10:30~12:30 |
15:30~18:00 |
|
第1回
7月14日
(日) |
第1回
7月6日
(土) |
第1章 認知症を理解する
①認知症とは?
②認知症の初期症状と種類
③認知症の病気と治療方法
④認知症のケア
第2章 認知症予防の基礎知識
①認知症は予防できるか
②認知症予防と食生活改善
③生活習慣病と認知症予防の危険因子
●「認知症予防の基礎知識」確認問題 |
第2回
7月28日
(日) |
第2回
7月20日
(土) |
第1章 食生活改善と認知症予防
①認知症予防に役立つ食事改善とは?
②認知症における食事の役割
③認知症と脳の働きと関係
④脳には刺激と栄養の両方が必要
⑤脳にとって望ましい食事とは
|
第3回
8月11日
(日) |
第3回
8月3日
(土) |
⑥認知症と活性酸素
⑦認知症と腸の働きとの関係
⑧認知症と神経細胞の働きとの関係 |
第4回
8月25日
(日) |
第4回
8月24日
(土) |
第2章 認知症を予防する食生活改善の実践
①食品摂取量と認知症予防の関係
②認知症を予防する脂肪の取り方
③脳と糖のかかわり
④認知症と糖尿病のかかわり
⑤血糖値を安定させる食事とは |
第5回
9月8日
(日) |
第5回
9月7日
(土) |
⑥乳製品と認知症予防効果
⑦豆類と認知症予防効果
⑧野菜と果物の認知症予防効果
⑨認知症を予防する食事のまとめ
⑩生ジュースの効用と作り方
●認知症予防食生活支援相談員と社会のかかわり
●「認知症予防の食生活改善の基礎知識編」確認問題
|
第6回
9月22日
(日) |
第6回
9月21日
(土) |
●模擬試験と解答・解説
●全体の振り返り |
|
|
■無料講座説明会
|
|
◎認定資格、認定試験、資格取得講座の内容について詳しく
知りたい方は、ぜひご参加ください。
|
|

※次は2024年6月
中・下旬募集予定 |
■横浜会場※ミニ授業あり |
| □開催日時/2024年6月23日(日)15:45~17:00 |
| □会 場/読売文化センター横浜(横浜そごう9F) |
| |
| ■大阪会場 |
| □開催日時/2024年6月29日(土)14:00~15:00 |
| □会 場/毎日文化センター大阪(毎日新聞ビル2F) |
|
|
|
| ★なお、参加ご希望の方は、電話、FAXで事務局までお申込みください。 |
|
|
| |
| |
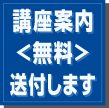 |
|
|
|
|
|
|
|
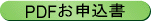 |
 |
| |
(プリントアウトして、講座名を選択しファックスか郵送にて
お申込み下さい) |
|
| |
|
|
|
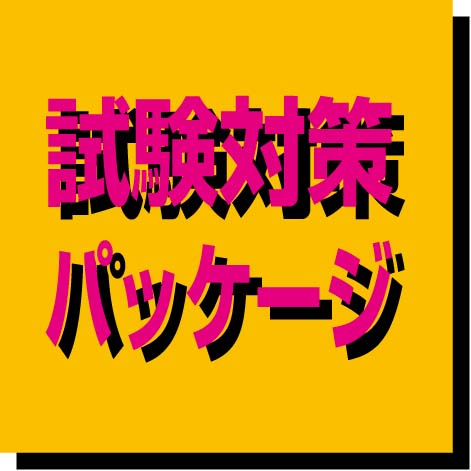 |
|
地域や時間の関係などで受講が難しい場合は、下記の「試験対策パッケージ」の
ご入が可能です。 |
|
| |
■内容:公式テキスト、模擬試験等、重要ポイント、その他試験に必要な資料
■料金:8,670円(税込み、送料込み) |
|
|
|
|
|
|
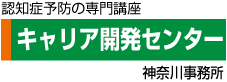 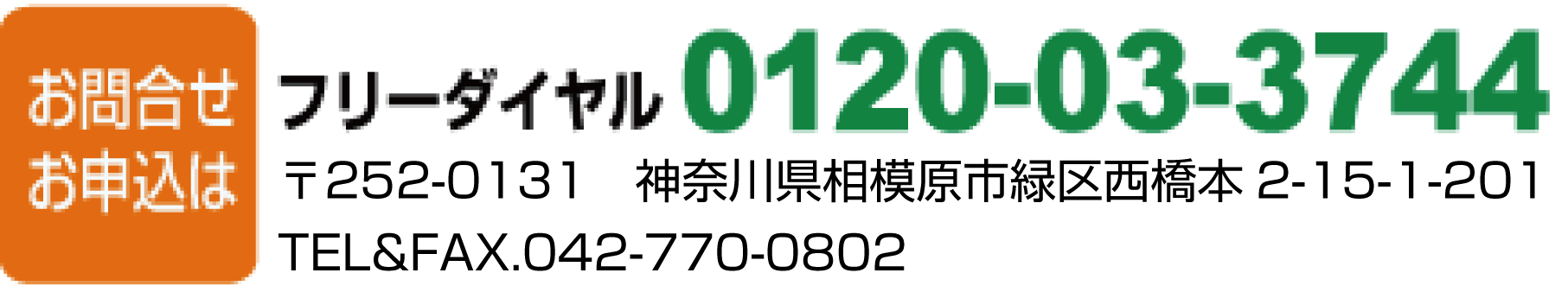 |
|
|
|
|